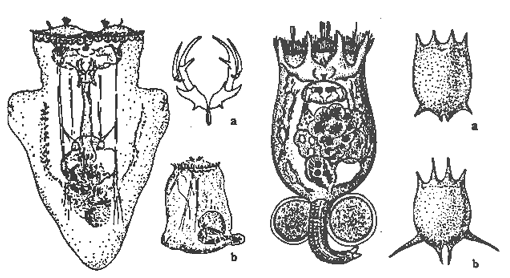CONTENTS
●ワムシは何者?
●何処に棲んでいる?
●飼うことはできる?
●生ワムシがあるでしょ
●淡水ワムシの利点?
●期待される淡水生物餌料
1.ワムシは何者?
ワムシは日本では約400種程度が知られており、そのほとんどが淡水に生息しています。
ワムシが属する生物門は『袋形動物門』で、これは大まかに言えばイソギンチャク(腔腸動物)とゴカイ(環形動物)の間に位置しています。
ワムシの分類例として、最大級のフクロワムシの一種とツボワムシを以下に示しました。現在流通しているワムシは元々汽水産の
Brachionus plicatilis(シオミズツボワムシ)と言うワムシです。
所属門:袋 形 動 物 門 (ASCHELMINTHES)
所属綱:輪 虫 綱 (ROTATORIA)
所属目:遊 泳 目 (Ploima)
所属科:フクロワムシ科 (Asplanchnidae)
所属属:フクロワムシ属 (Asplanchna)
学 名:Asplanchna sieboldi (アスプランクナ・シーボルディ)
所属科:ツボワムシ科 (Brachionidae)
所属属:ツボワムシ属 (Brachionus)
学 名:Brachionus calyciflorus (ブラキオナス・カリシフローラス)
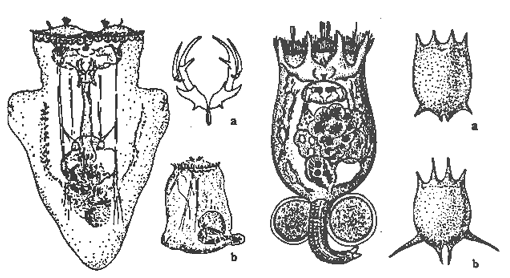
図1 Asplanchna sieboldi (左)と Brachionus calyciflorus (右)の形態
新日本動物図鑑より
2.何処に棲んでいる?
ワムシの多くは淡水生活を営み、環境変化に強く、広適応であるため、ワムシがいない所の方が少ないと考えたら良いでしょう。例として、
① 手入れの悪い花瓶の中
② 水槽のフィルターの中
③ 排水管の中
でも発見できますから、川や池には必ず生息しています。もしもワムシがいない水域があれば、ここは危険水域だと考えたほうが無難です。
3.飼うことはできる?
ワムシを飼うのは簡単ですが、培養するのは簡単ではありません。
ワムシを飼育したければ、池の水を1ι以上の容器に8割程度採り、窓辺に放置します。
夜、水の表面に光を当てて、表面付近をスポイトで吸いとって観察すればワムシが泳いでいるのが分ります。
他にミジンコやケンミジンコの仲間も見られますが、ワムシはこれらよりもはるかに小さいので、顕微鏡で観察する必要があります。
この状態で1週間程は飼育が可能です。しかしながら時間がたつと、餌になるバクテリアや微細藻類が消失
していきますのでワムシも消滅していきます。ワムシを利用したければ、培養する必要があります。
4.生ワムシがあるでしょ
現在、養殖を中心に出回っているワムシは元々汽水産のBrachionus plicatilis(シオミズツボワムシ)
と言うワムシです。今から30年程前に三重大学の伊藤先生が培養したのがきっかけで広く利用されるようになりました。
Brachionus plicatilisは研究暦が長く、利用に関しては完成された技術がありますので、あまり専門的
でない人でもある程度の培養が可能です。しかし、餌となる単細胞藻類の無菌培養施設や温度調整可能な培養室が
ないと何時かは消滅する運命にあります。でも、購入が可能なので心配はいりません。また買えばよいのです。但し、
Artemia salinaにも言えることですが、臨海施設でない限り海水の調製が面倒で、また淡水生物の飼育には必
ずしも万能ではありません。
それならば淡水のワムシを利用すればいいはずです。ところが何故か、淡水のワムシは研究機関が一時的に研究材料にする
ことはあっても、本格的に利用されてはいないのです。
5.淡水ワムシの利点?
淡水のワムシが淡水生物幼体の餌料に利用できる場合の利点として次のことが考えられます。
① 必ずしもろ過の必要が無くなる
培養容器の上面から光を当てれば集まってくるので、これを容器ですくい取って利用できるようになる。ワムシは
100~300μm(0.1~0.3mm)と小さいためろ過が面倒です。汽水(海)産のワムシを同じ方法ですくうと海水が飼育容器に入って
しまいます。これが問題とならない場合や、ろ過が面倒でない人には利点とはなりません。
② 飼育容器内で生存する
汽水(海)産のワムシを淡水に入れると、浸透圧の影響で死滅していきます。淡水のワムシは本来が淡水産ですので、これが原因で
死ぬことはありません。水槽内の水質悪化を防止します。但し、ワムシが死滅しても問題とならない場合もあると思われますので、
絶対の利点にはならないかも知れません。
③ ワムシの餌を同時に与えることでワムシがフィルター内に生息する
淡水ワムシの餌は淡水の単細胞藻類です。これを同時に飼育水槽に与えることで、ワムシはフィルター内で増えることになります。
特に珪藻を用いることでこのことはより確実になります。ツボワムシの仲間は付着する性質も兼ね備えています。フィルター内にしが
み付いて、デトリタス(ゴミ)やバクテリアも捕食します。増えたワムシはフィルターから泳ぎ出て、淡水生物幼体の餌料になります。
要するにフィルターがワムシフィルターとして機能します。以前、このような発想のフィルターがありましたが、フィルターだけでは
必ずしもワムシは増えませんでした。
④ ワムシの餌を同時に与えることでこれ自体が餌になる
汽水産のBrachionus plicatilis(シオミズツボワムシ)の餌は基本的には海産クロレラです。同時に与えるとシオミズツボワムシ
同様、浸透圧の影響で死滅していきます。
淡水ワムシの場合は淡水クロレラ等の淡水緑藻を与えることで培養が可能です。淡水緑藻は淡水環境で生存可能ですので、水槽内の
壁面やフィルターに付着します。特に草(藻)食性の稚エビには直接エサとなり、同時に色揚げ効果もあります。
⑤ その他の利点
その他の利点はシオミズツボワムシの場合と同じと考えて結構です。ワムシの餌になる単細胞藻類の培養液にビタミンB12やEPAを添加
することでワムシが栄養強化され、飼育生物の歩留まりが向上します。この他にも利点があれば同様に考えて結構です。
6.期待される淡水生物餌料
このようなことを考えると、淡水生物幼体の餌料に『淡水ワムシ』を与え、淡水ワムシの餌料に『淡水藻類』を与える技術が整えば、
これまで難しいとされてきた淡水生物の飼育(増殖)が比較的簡単になるかも知れません。
今回供給可能なワムシは、ツボワムシ(Brachionus calyciflorus)と言う淡水ワムシです。供給量や価格の面では課題が残りますが、
淡水養殖(飼育)の世界では画期的技術となると自負しています。このツボワムシ以外にも、淡水性のフクロワムシやコガタツボワムシ
についても培養可能の目処が立っています。ご期待ください。
【お問合せ】
 |
お問合せページへ |
|
|
|
|